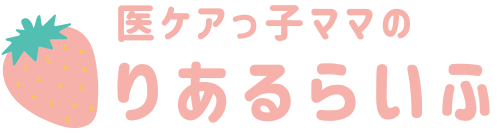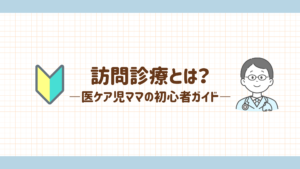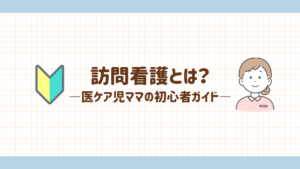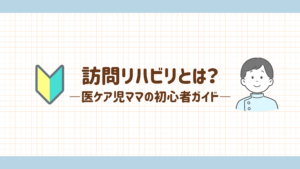NICUを退院して、在宅生活が始まったあの日。
嬉しさと同じくらい、緊張や不安も大きかった。
娘が息をしているかさえ気になって、眠れない夜もあった——。
この記事では、在宅医療が始まってからの約1年を振り返りながら、支えてくれた人たちや、少しずつ掴んでいった“日常”について書いていきます。
在宅生活が始まってからの不安と感謝

NICUを退院してから最初の3ヶ月は、義実家でお世話になっていました。
最初から二人育児ではなく、ハードルを少し下げてくれた夫の計らいには今でも感謝しています。
義母の手も借りながら、家事を任せきりで申し訳なかったけれど、そのおかげで娘のケアに集中できました。
眠る時間も少しはとれるようになり、精神的にも助けられた日々でした。
3人で自宅に戻った日、娘を連れて帰れた喜びと同時に、強い緊張感もありました。
「娘の異変に気づけるのは自分しかいない」
医療的ケア児のママは、まるで我が子の専属ナースのような存在。
命を守る責任の重さに、押しつぶされそうな日もありました。
支えてくれた人たちの存在

それでも、私ひとりで抱え込む必要はありませんでした。
在宅生活には、たくさんのサポートがあることを知りました。
- 往診(週1回):先生が自宅で診察し、必要な検査や薬の処方もしてくれる。
体調の変化を一番そばで見ているのは私だから、気づいたことを積極的に伝えるようにしています。
制度の診断書などもお願いできます。 - 訪問看護(週3回):看護師さんが1時間ほど来てくださり、体温測定、ミルク注入、浣腸や吸入、経管栄養チューブ交換補助などを行ってくれます。
娘の状態を一緒に確認しながら、私はその間に夕食の支度をすることも。 - リハビリ(週1回):関節が硬くなりやすい娘にとってはとても大事な時間です。
体を動かすほか、音や光に反応する練習、手足のマッサージも。
機嫌がいいときは目をパチクリさせて積極的に頑張る娘の姿に、いつも励まされます。
それぞれについて詳しくまとめた記事もぜひご覧ください。
おうち時間と娘の笑顔

お出かけはあまり多くありません。
外はまぶしくて目を開けられないこともあるし、酸素やモニターの持ち運びは大変です。
それでも、調子が良いときは2時間ほど機械を外して、神社や公園に行くこともありました。
桜やチューリップを見に行ったり、車でスーパーに買い物に行ったり。
ほんの少しの外出でも、娘と一緒に過ごせる外出時間は特別でした。
家では、抱っこして頬をむにむにしたり、テレビを見ながら話しかけたり。
クリスマスや誕生日、ひな祭りには飾りつけをして、お気に入りの帽子で記念写真。
娘の笑顔があれば、どこにも行かなくても幸せでした。
在宅生活を通して伝えたいこと

在宅医療のママたちに伝えたいのは、「ひとりじゃない」ということ。
往診や訪問看護、相談員、保健センターなど、頼れる制度や人はたくさんあります。
手続きをして、助けを受けていい。
不安を抱えたまま頑張り続けるより、誰かと支え合う方が、子どもにもママにも優しい。
この1年で、私は少しずつ自信を持てるようになりました。
そして、娘が見せてくれる笑顔が、そのすべてを報いてくれています。
次の記事では、娘が1歳半までの頃、どんな1日を過ごしていたのかを振り返って書いています。